2025年の議会活動
12月定例会/11月28日開会
12月16日閉会

【12月定例会が終わりました】
代表質問から最終日の討論まで山あり谷あり。食欲が落ちるほど緊張した日々でした。
補正予算第5号には原案賛成しましたが、いろいろ削除する修正案が可決。議会は多数決なので仕方ないのですが、このあとのことを心配しています。
①中学校部活動の地域移行にかかる経費は全額削除されました。来年4月から平日と土日を全部地域移行する奈良市方式で、準備期間が短い中であっても、全力で進める必要があったと思います。予算削除で、4月以降部活動がどうなるのか全く読めなくなりました。4月から教員に休日の手当が支払われなくなるので(これは県の方針)、タダ働きをしてもらうわけにはいきません。こどもたちに不安を抱かせるようなことがあってはならないと思います。
②こども医療費の無償化拡大は、子育て支援の大きな政策課題。500円の窓口負担をなくす方向に異論が出て削除されました。この議論の中でコンビニ受診や過剰受診という発言があったことは残念でした。無償化を進めることで医療費が増えるといわれていますが、経済的理由で受診を控えていた人が本来必要であった受診が確保された結果です。
③学校体育館の空調設備は、小学校40校分の予算を残して中学校その他分は削除。電気式はコスト重視の選択でしたが災害時の対応などで異論が出ました。
立場の違いがあるなかで、議論を尽くそうとする議会になったことは12月議会の良かったところでした。
(2025.12.16)

【12月4日 代表質問します】
12月3日から3日間、代表質問・一般質問が始まりました。
私は4日(木)午前11時頃から代表質問を行う予定です。ぜひ、インターネット中継をご覧になってください。
【質問事項】
1.物価高騰の中での高齢者の生活
2.クリーンセンターについて
3.学校給食無償化について
4.子育て支援の拡大について
5.不登校支援について
6.外郭団体への公的責任拡大について
(2025.12.3)
【12月定例会 始まりました】
11月28日から12月定例会が始まりました。
来週に代表質問、一般質問があります。
市民の声を届けたいと思って質問準備をしています。
今回は、市長に質問する代表質問となります。ぜひご注目ください。
(2025.11.28)

【市長に要望書提出】
11月20日、会派(市民ひろば)として仲川市長に2026年度予算に向けた要望書を提出し、意見交換をしました。これから12月定例会が始まります。来年度予算編成に向けての動きも本格化していきます。
市民の皆さんから寄せられた声をできる限り反映させるよう頑張っていきます。
(2025.11.20)
【議会運営委員会】
きょうは議会運営委員会で「議会ハラスメント防止条例」の制定に向け議論をしました。全国の自治体のうち、今すでにハラスメントに特化した条例が134団体142条例が作られています。
背景には、社会全体でのハラスメント認識の高まりがあり、民間の次は自治体へと波及をしている状況があります。後から作るのだから一番いいものを作りたい。そう思っていろいろ意見を言いました。
持ち帰りになった課題もありましたが、前文とSOGIハラスメントについては検討していただくことになりました。
(2025.11.17)

【立冬の日に】
11月7日は立冬。この前キンモクセイが咲いたばかりなのに季節は進んでいます。市役所は暖房がまだ入らず、控室にいるととっても寒い。
今日は議会のハラスメント防止条例制定に向けた会議があります。各議員、各会派から沢山意見が出されていて、それをひとつひとつ取り上げ協議をしていく予定。時間をかけて合意形成を図ることはとても大事なことです。
私たちは条例の前文が必要ではないかという点、ハラスメントの定義についての意見を出しています。
(2025.11.7)
9月29日に9月定例会が閉会しました。
9月定例会が開会しました。
9月5日・開会
9月10日・代表質問
9月11日・一般質問
9月12日・一般質問(阪本みちこが質問しました)
9月18日・厚生消防委員会(阪本みちこ所属委員会)
9月29日・閉会

9月定例会 閉会しました
9月議会が29日に終わりました。
物価高騰対策として水道・下水道基本料金の3ヶ月無料化が決まりました。また新クリーンセンター建設に向けた候補地3ヶ所の調査費(補正予算)は今議会では予算として認められず、継続審査となりました。遅れれば遅れるほど工事費用は嵩むのではないかと思いますし、調査をしないことには始まりません。
他にも賛否が別れた議案には、議長の議員報酬を他の議員と同じ議員報酬に引き下げる提案でした。維新の議長として公約の一環だったのでしょうが、特別職の報酬を審議する審議会にはかることなく、任期中だけの削減は、疑問符がつきます。他の議員より高い議員報酬であっても、議長の職責を果たしていただければそれでいいのではないですか。ただ、財政負担軽減に寄与する点で、賛成しました。
議会運営委員会で3つの意見書決議案を提案しました。①生活保護基準に夏季加算を設ける意見書案、②国民健康保険における子どもの均等割り免除を求める意見書案、③子ども版「初めての防衛白書」の取扱いに関する意見書案です。
詳細は別の機会にします。
採決では、重い判断が連続し、長丁場でしたが、なんとか無事に終わることができました。
(2025.9.29)

【厚生消防分科会】
各分科会に別れて議案審査が始まり厚生消防分科会で質問をしました。
◉市立奈良病院の経営状況について~2500万円の黒字決算であったが、全国的に86%の自治体病院が赤字になっている
◉市立看護専門学校について~卒業生の6割が市立奈良病院に就職
◉産後ケア事業について~利用料を下げ、オンライン申請にしたことで利用が拡大等々。
事業の効果をはかる決算の質疑、骨が折れることですがようやく面白いと感じています。
(2025.9.18)
【厚生消防分科会質問・市立奈良病院の経営状況について】
全国自治体病院協議会が、8月6日に2024年度決算で全国にある自治体病院の内86%の病院が経常赤字だったとの調査結果を公表したことから、市立奈良病院の経営状況について質問しました。
➊奈良市は一般会計から毎年病院を建設した際の企業債返還のための資金(1億8千万円程度)と交付税を病院事業会計に繰り出し、病院事業会計としてはそれをそのまま支出しています。市立奈良病院は指定管理者(公益社団法人地域医療振興会)によって運営されているため、この特別会計では病院の経営状況が分かりません。市立奈良病院の経営状況の現状の説明を。
(市答弁1)病院本体の決算状況については、令和6年度の最終的な決算として、税引前当期利益は2,584万2,427円の黒字を計上しています。
❷今回何とか黒字であったけれども、物価高騰や人件費高騰の影響は大変大きく、来年度決算にどのように影響を与えるか。
(市答弁2)市立奈良病院の場合、入院収益や外来診療収益など医業に係る収益が、令和6年度決算では129億2,942万4,428円、令和5年度決算では125億154万5,788円となっており、収益の確保に尽力していただいているところではあるが、一方で事業費用の増加も避けられない状況であり、全国多くの自治体病院と同様、今後も厳しい経営状況になるものと認識しています。
※意見
医業にかかわる収益の確保に尽力していただいているが、事業費用の増加が避けられず、厳しい経営状況が予想されるという説明でした。
❸経営面にも影響を与えると思われる職員配置数は、R4年とR6年の比較をすると、看護師が45人減少(看護助手を含めると50人減少)しているが、病院の運営に影響を与えていないのか。(例えば入院患者を受け入れできないとか、病棟を一部閉鎖しているとか)
(市答弁3)急性期医療を担う病院として、救急や重篤な病気に対して高度に細分化した医療を提供する上で、看護師の職員数が募集人員に対して不足傾向にあると考えており、病棟看護師の勤務状況や経験年数等を勘案し、病棟単位で全ての病床を運用できない場合は、入院患者を他の病棟へ振り分け、病棟や人員を整理・集約して運用していますが、人的に余裕がある状態では無いため、病院の機能を100%運用できない等の影響があるものと考えています。
※意見
病棟を集約しているという答弁だったが、人が少なくなると業務負担が大きくなる、これも大きな問題で離職につながることも考えられます。地域医療の中核としての役割を果たすことができるよう、看護師不足にはしっかり取り組んでいただきたい。
(2025.9.18)

【一般質問事項】
1 議案第78号 奈良市一般職の職員の給与に関する条例の一部
改正について及び議案第79号 奈良市職員の退職手当に関する
条例の一部改正について
2 会計年度任用職員の処遇について
3 報告第42号 住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算の
認定について及び報告第51号 奈良県住宅新築資金等貸付金回
収管理組合市町村特別会計(奈良市)歳入歳出決算の認定について
4 人工芝のマイクロプラスチック問題について
(2025.9.12)
【一般質問・人工芝のマイクロプラスチック問題について】
プラスチックごみが紫外線などの影響でもろく小さくなり、5㎜以下の小さなプラステチックのかけら(マイクロプラスチック)になり、環境に負荷を与えることが知られるようになっています。海に流出して、魚がこれを食べることによる食物連鎖を通じて、有害化学物質が生き物の体内に蓄積する可能性も懸念され、人間の健康にも大きな影響を与えることが問題になっています。
そのマイクロプラスチックの発生源としていま注目されているのが人工芝です。人工芝は天然芝に比べて管理がしやすくあまり費用が掛からないことから、野球場やサッカー場などのスポーツ施設、公園、学校のグラウンドなどによく使われているようです。この人工芝の奈良市のスポーツ施設での使用状況について質問しました。
➊奈良市のスポーツ施設において、人工芝はどこに使用されているのでしょうか。
❷奈良市においてすでに使用している人工芝について、どのような対策をするのか。今後の対策や廃棄方法について、また寿命がきたときに次も人工芝にするのかどうか、市の方針は。
❸今後このマイクロプラスチックの発生を抑制することや市民への啓発をどのように行っていくのか。
(市答弁1)奈良市のスポーツ施設ではテニスコートで砂入り人工芝を使用しています。
(市答弁2)一定期間使用し劣化した人工芝については張り替えを実施しているが、人工芝の適正な使用と管理の徹底に努めながら、環境負荷の低減に向けた取り組みを進めてまいりたい。次回張り替えについては、環境負荷の少ない方法を研究してまいりたい。
(市答弁3)適正に処理されなかったプラスチックがマイクロプラスチックとなり環境汚染の原因となることを理解し、プラスチックのリデュース(排出抑制)に視点をおいた啓発も進めていくことが必要。今後、市のホームページやしみんだより等を利用し、市民に向けた周知啓発を進めていきたい。
※意見
海洋プラスチックの問題は世界で深刻化しており、人工芝のマイクロプラスチック流出問題を、今後市民の皆さんに啓発をしていただきたいし、すでに人工芝を使っているところはしっかり対策をとっていただきたい。次の張替え時にどうするのかは製品情報を見て考えるという答弁でしたが、天然芝はヒートアイランドを緩和するとも言われていますし、安全性を優先した選択をお願いしたい。
(2025.9.12)

9月定例会 代表質問・一般質問
きょうまで3日間にわたって代表質問、一般質問が行われ、30人が質問に立ちました。(とても多い。皆さん気合いが入っています。)
私は、フレックスタイム制や人工芝のマイクロプラスチック問題について等の質問をしました。新人議員の方からは、奈良市の医療課題について専門的な立場からの切り込みがあったり、また、メガソーラーに関して3人の議員から質問があり、これは今後のテーマとして注目されます。
もうひとつ注目の新人議員。テレビ局のカメラが4台も来ていました。予想通り鹿のことを質問し、市長の答弁に対して、大きな声を出していましたが、議場でこんな経験は初めて。
(2025.9.12)

【9月議会が開会しました】
市長からは30分くらいかけて決意と所信の一端が示されました。
こども医療費助成の拡大で、就学前の無償化をめざすという発言があり、大歓迎です。この課題は市民から要望があり、私は選挙の公約にあげていましたので。
また、クリーンセンターの計画を一旦白紙に戻してほしいという請願が建設反対の会から出されてきました。これは「ごみ焼却施設等特別委員会」に付託されます。9月議会は波乱の予想です。
なお、9月12日(金)一般質問で質問にします。予定では、午前の時間帯です。
(2025.9.5)

議案説明会
9月議会に向けた議案説明会がありました。
物価高騰対策には、水道・下水道料金の基本料金の無料化を3ヶ月実施する提案がされ、議員34名の要望書は実を結んだ形となっています。
補正予算では、クリーンセンター建設候補地3ヶ所の調査費8千6百万円が遂にあがってきました。これが今回一番の注目点です。
きょうの議会運営委員会で会期は9月5日から29日までの予定となりました。暑い議論の夏(秋)はこれから始まります。
(2025.8.29)

第2回クリーンセンター建設懇談会
前回より出席議員は少なめでした。
前回に出された質問に答える形で、過去と現在の策定委員会の評価基準の変更点、広域化に向けた他の市町の対応はどうだったのか、等が説明されました。
特筆すべきは、市長から将来的に広域化に向けた積極的な発言があったことです。詳細は9月議会の議論に委ねますが、注目をしています。
お弁当のあと、9月議会に向けた質問調整を行いました。
(2025.8.27)
新クリーンセンター建設3候補地視察(2025.8.26)
新クリーンセンター建設の3候補地視察に行きました。議員20数人が参加。

①大和田町
平地が少しと大和郡山市境まで続く山林がその場所でした。大部分が砂防指定地であること、丸山の住宅地を通らないで進入路をどう敷設するか問題がある。
(2025.8.26)

②七条町
想定する煙突の位置は大和郡山市との境ギリギリのところで、目の前に郡山市清掃センターの煙突が見え、余りに近くてあらためて驚きました。
(2025.8.26)

③北之庄町
田んぼが広がる風景でしたが、農振農用地の指定を受けているため、それをはずすことができるのか。また、住宅地との距離が取りにくいという問題があります。
(2025.8.26)
8月臨時議会(2025.8.19~21)

【8月臨時議会が閉会しました】
新議員による議会の体制を決める8月臨時会が閉会しました。私は今後1年間、厚生消防委員会と議会運営委員会に所属します。
今回のトピックスとして、へずまりゅう氏の通称使用が議長により認められたことがあります。奈良市議会は明文化したものがなく、今後検討されていきます。元々は女性議員の結婚離婚にかかわり、参議院で早くから通称使用が認められ、その後、芸名やペンネームが広く認められています。通称使用は時代の流れであり、賛成です。
議会内で戸籍名しか使えないなら、立候補した人物と議会で活動する人物が同一であることを認めることが難しく、また、社会的な活動をどの名前でしてきたか、アイデンティティーにも関わることです。これは選択的夫婦別姓の議論と通じるものがあると感じました。
来週の29日にはもう次の9月議会の議案説明が行われることになっていて、あわただしく8月が過ぎて行きます。
小中学校の夏休みももう少しで終わりですね。
夏の思い出~映画「国宝」を見たこと、賢島に出かけたこと……です。
(写真は賢島の英虞湾)
(2025.8.12)

【8月臨時議会】
8月臨時議会が開会しました。
臨時議長は年長議員の松石さんでした。市長は挨拶で「議会とは車の両輪」と述べられましたが、その事が実現する議会になることを願っています。
議長選挙では、維新の立候補者が議員定数と議員報酬の見直し(削減)をあげていたため、それには賛同できず、違う選択をしました。投票の結果、奈良市で初めて維新の議長が誕生しました。
その後、市長に物価高騰対策として水道料金、下水道料金での減免を行うよう、6会派と無所属議員34名(39名中)の署名を手渡ししました。
3月議会においても、物価高騰対策はプレミアム商品券より水道料金でと提案しましたので、このような議会対応につながったことをとても喜んでいます。
(2025.8.19)
新会派を結成
新会派を樋口清二郎市議、柿本元気市議とともに結成しました。会派の名前は
「市民ひろば」です。
議員総会(2025.8.12)

【3期目がいよいよスタート】
議員総会が開かれ全議員が集まりました。年長議員の松石さんが主宰者をつとめられ、議事が進行しました。
議員紹介で、この場に参加できなかった人たちのことをふと思いました。そうであればこそ、余計頑張らないと。ファイト
議場での席や会派の部屋も新しくなります。
皆さん、応援よろしくお願い致します。
(2025.8.12)
定例議会・常任委員会
6月定例会/6月3日開会・6月17日閉会

6月議会・閉会
6月議会は、きょうようやく最終日を迎え、すべての議案が賛成多数で可決されました。
賛否が分かれたのは、職員の勤務時間について「フレックスタイム制」を導入する件、神功小学校の跡地を3億円で売却する件でした。フレックスタイム制については人材確保の点から反対するものではありませんが、今も課題がある職場の人員不足などを解消していくことが合わせて必要だと思います。
嬉しい話①は、私たちの会派から提案した「物価高騰への対処を求める意見書」が採択されたことです。ガソリンや電気代高騰への対策、最低賃金の引上げ、自治体への臨時交付金を求めるなど欲張りな内容です。奈良市議会の意見書は提案してから2回の議会を経る必要があり、機動性に欠ける点はありますが、ようやく採択されて良かったです。今度の参議院選挙の争点になる物価高騰対策に、2万円給付か消費税の引き下げか、皆さんは何を求めるでしょうか。
嬉しい話②。3月議会で戦後80年を機に、市役所敷地に広島の「被爆アオギリ」と長崎の「被爆クスノキ」を植樹してはどうかという提案をしましたが、担当課に聞きますと、実現の方向で動いているということでした。涙が出るほどうれしいことでした。
終了後、議会控室の片づけをして私物は全部持ち帰りました。これから全力で選挙に臨みます。
(2025.6.17)

【6月定例会・一般質問】
一般質問を行いました。質問項目は次の通りです。
幼保再編計画(令和4年度修正版)の見直しについて
①公立園を幾つか残すことを受けて、計画見直しの必要性について
②今後に向けた新たな公立園の役割について
③公立保育所等を施設整備する際の国の財政支援について
(2025.6.10)

6月議会/代表質問・一般質問
先週から3日間の代表質問と一般質問を通して、多くの議員が取り上げた課題は、ひとつは米不足問題でした。米を安定的に生産してもらうための農家への所得補償、価格補償や、若い世代が農業に参入できるよう障壁を取り払うことなどが意見として述べられています。
部活動の地域移行についても何人かの議員が取り上げました。地域の側の受入れ体制が不十分ではないか、という意見には共感しました。
新クリーンセンター建設計画について、策定委員会から答申が出され、七条地区を始め3か所が示されましたが、それに対する議論は十分だったとはいえません。市長も議員も任期満了を目前にして地についた議論ができにくい状況でした。
私自身は、公立園をゼロにする幼保再編計画について、「公とは何か」「公立保育所の役割とは」を市長に質問しましたが、なかなか噛み合わない議論でした。
今期で勇退する4人の議員から、質問と合わせてご挨拶があり、感謝のことばが述べられました。共産党の井上議員は「22年間、貧困との闘いでした」と話始め、「議員をやって良かった」事例として、夫亡きあと妻が市営住宅の継承をするため連帯保証人が立てられないことを議会で取り上げたことをあげていました。そして最後に「市民のくらしの困難に向き合う市政であって欲しい」という言葉で締めくくられました。議場は大きな拍手に包まれました。
先輩方のことばをしっかり心にとどめておきたいと思います。
(2025.6.10)
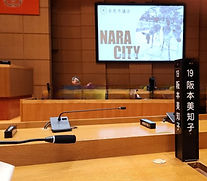
6月議会が始まりました
6月議会が始まりました。4年任期の最終です。気合いを入れて頑張ります!
報道陣が多く待ち受けておられましたが、市長からは進退について言及はありませんでした。
懲罰特別委員会の報告が行われ、居眠りをした議員に対しては、誠実に職務を行うという点で、また議会の品位を尊重するという点で懲罰を科すべきとし、「公開の議場における陳謝」が満場一致で採択されました。
その後、当の議員により「誠に申し訳ございません」と懲罰文の読み上げがあり、一連の事態は終了しました。
任期最後の6月議会は、議員の皆さんが、市長との論戦に向けて、てぐすねを引いてこの議会に望まれることでしょう。パワー溢れる議会になりそうな予感です。ぜひ皆様、傍聴やネット中継をご覧になって下さい。
(2025.6.3)
定例議会・常任委員会
【3月議会 閉会】
年度末最終日までかかって、きょうようやく3月議会は閉会しました。市長の閉会挨拶ではミャンマーの地震に対するお見舞いの言葉がありました。募金は市役所内で開始されています。
(2025.3.31)

延長議会・深夜まで
議会は23時に再開しました。きょう中に終わるはずでしたが、いろいろあって31日(月)まで延会になりました。理事者の皆さん、議会事務局の皆さん、お疲れ様でした。
附帯決議は賛成多数で可決されました。佐保小学校の建設にかかる工事請負契約が成立したうえで、鼓阪小学校の統合に関して保護者、地域の合意に向けて丁寧に進めてほしいという内容で、それは当然のことです。
続けて市長の問責決議が提案され、私は反対しましたが、賛成多数で可決されました。飛鳥公民館、総合福祉センター、七条のクリーンセンター建設、鼓阪小学校の統合等々の問題でその度に請願が出されてきたことは、当事者の合意形成を図らず強引な行政運営を行ってきたことが原因である。それには頷くところがありますが、ただ問責決議のレベルやタイミングが腑に落ちない点があり、賛成できませんでした。
今後市長はこの問責決議をどのように受け止めていくのでしょうか。
(帰宅するために車に乗り込んだ時間は、11時43分でした。)
(2025.3.28)

再提案・予算案
市長が出し直して提案した予算案です。
市長が再度提案した予算案は賛成25、反対11で可決されました。プレミアム付き商品券は削除されたことは評価します。公共交通事業者への燃料費高騰補助金3000万円を削ることに異論が出ました。今後事業者の対象や規模を見直し、再検討するという市長の言質を確認して賛成しました。
この後、附帯決議が提案され質疑もありました。これは鼓阪小学校の統合に関して保護者、地域の納得を得られるよう慎重に話合いを進めてほしいという内容です。
午後11時59分まで会議時間が延長されました。初めての経験ですが、昔はよくあったと先輩議員から聞きました。まだ、討論と採決があります。
(2025.3.28)
【会期が3月31日まで延長】
議会が再開し、一昨日の予算決算委員会の否決を受けて、市長は予算原案を撤回しました。議会からの指摘を受け止め、市民生活に影響が出ないようにしたい、とのことでした。明日には予算案が示されますので注目しています。会期は31日(月)まで延長されました。
もうひとつ注目点として「地域公共交通基本条例」が提案されましたが、可否同数で議長が採決に参加して否決となりました。
利用者の減少傾向に対して、地域の公共交通を維持確保することが、自治体にとっての課題になっており、利用を促進するための理念を示した条例案でしたが、「市民の役割」の項で、「市民は公共交通を積極的に利用するように努めなければならない」と言う点に、利用を押し付けているという批判が出されました。
公共交通の利用促進施策に協力するという市民の立場を示しているものだと思いますが。否決は残念です。より良いものになって、再び提案されることを願っています。
(2025.3.27)
【予算決算委員会の採決】
会議時間を夜8時まで延長して、議長と委員長以外の35名が採決に臨みました。(本当は委員長も入っています。賛否同数の場合は)
共産党提案の予算組み換え動議と他の予算修正案2つが賛成少数で否決され、なおかつ原案も否決がされました。どの予算も通らない、こんなことは今までなかったそうです。27日の最終日に向けて、予算案成立に向けた議会と市長の歩み寄りが必要です。
(2025.3.25)
3月議会・行革特別委員会
東日本大震災から14年の今日、行革特別委員会は黙祷から始まりました。
鼓阪小学校の在校生2人と、保護者の方から合わせて3つの請願が出されて、これで佐保小学校と鼓阪小学校の統合に関し5つの請願になりました。
子どもたちは統廃合に関して「生徒の意見を聞かないで統合を進めてほしくない」と意見を表明しています。小学生で請願を出すことはとても勇気がいったことだと思います。しっかり受け止めていきたいです。
(2025.3.11)
3月議会 会派を代表して質問しました
3月6日、会派(新世の会)を代表して質問しました。
※一部詳細を掲示。
【質問項目】
1 新年度予算について
目指すべき物価高騰対策について
白菜、キャベツが2倍の値段に、お米は、値上がりしたままスーパーの店頭で品薄になっています。くらしを直撃している現在の物価高騰の背景には、賃金が上がらず物価に追い付いていない「失われた30年」の問題、また年金は目減りをし、一方で税と社会保険料などの国民負担率が50%を超えているにもかかわらず、将来への不安が解消されないことがあります。「スーパーに行かないことが一番の節約の方法だ」という声や、「国民健康保険料を払うために生命保険を解約した」という市民の声をこの間聞いてきました。
このような市民の生活を守るために、来年度予算で目指すべき物価高騰対策について質問しました。
市長:今回のプレミアム付商品券発行事業の事業費は6億6500万円、プレミアム率は20%として前回から抑える一方で、発行冊数を大幅に増加させることで、できる限り多くの世帯に購入いただきたいと考えている。
市長:この事業は、物価高騰に直面する市民の家計支援を目的としているが、同時に地域経済の活性化も期待しているものである。
阪本意見:今必要な政策は「経済をまわす」ことではなく、物価高騰の影響を受けて生活が苦しくなっている人たちに対する「生活応援」を、一部の人だけでなく公平にいきわたらせる政策ではないかと考える。そのためには、以前実施した水道料金の基本料金の減免は物価高騰対策臨時交付金の推奨事業メニューQ&Aにも挙がっており、それにふさわしいものだ。「税金は公平に使われるべき」であり、市長にはもう一度立ち止まって再検討されるよう強く要望する。
2 奈良市を平和への思いがあふれるまちにするために
戦後80年と非核平和都市宣言を生かした取組について
3 防災・減災の取組について
避難所運営ガイドラインとスフィア基準について
阪神淡路大震災から30年がたちましたが、昨年の能登半島地震においても避難所の環境について、いまだに雑魚寝であると、日本の対応が遅れていることが指摘をされています。石破首相は昨年11月の臨時国会の所信表明演説でスフィア基準についてふれ、「発災後、全ての避難所で基準を満たすことができるよう進める」と表明しました。スフィア基準は紛争や災害による被災者に対する「人道憲章と人道対応に関する最低基準」とされています。その基準によれば、1人当たりの居住スペースは3.5㎡、飲料水は最低15リットル、トイレの設置は20人に1つ以上、男女比は女性は男性の3倍必要だとしています。
これまで奈良市は148か所の指定避難所で51、000人の避難者を収容できるとしていましたが、もとになる一人分のスペースが2㎡から3.5㎡と1.7倍に大幅な見直しが行われることから、現状では29,142人分が確保されていることとなり、避難所の在り方の見直し等が必要になっていると考えます。またトイレの確保や、キッチンカーなどによる食事の質の確保など、避難所の環境改善に大幅に踏み出すことが必要になっています。
阪本:スフィア基準を反映した政府の「避難所運営に関する取り組み指針・ガイドライン」の改定を受けて、奈良市として「避難所運営ガイドライン」にどのように反映するのか。
市長:これまで一人あたり2㎡としていたが、能登半島地震で推進された広域避難や、1.5次避難所の開設、一人あたり3.5㎡の居住スペースを確保するよう、本市の避難所運営ガイドラインに反映させていく。
市長:トイレの確保については、内閣府が示す目標値を達成できるよう、協定業者等から速やかに調達を行う他現在確保できているトイレに加えて、マンホールトイレを令和7年度以降、順次、整備を開始するなどして各避難所等へのトイレの配備をすすめる。
阪本意見:スフィア基準は、避難所は耐え忍ぶ場所ではなく、家族や家を失った人たちが生活再建のために少しでも前向きになれるような場所にしていかなくてはならない、そのための最低基準であるということです。数値目標が大きく目につきますが、決してそうではなく、「被災者は尊厳ある生活を営む権利がある」という理念がいっしょに広く伝わっていけばいいと思います。
これまでの避難所運営ガイドラインを見直し、必要スペースを3.5㎡に見直していく、という方向が答弁でありました。いざというときに質の高い避難所を作るため、事前に十分な準備をしておくことが必要だと思います。
4 奈良市の行政経営の将来ビジョンについて
5 高齢社会におけるごみ収集の在り方について
高齢、障がいなどの理由により、一般家庭ごみなどを指定場所に出すことが困難な世帯のために、職員が玄関先でごみの収集を行うことを「ふれあい収集」と称して各自治体で実施されています。すでに中核市62市のうち41市(66%)で実施しています。また奈良県内11市の内7市(63%)が実施しています。
阪本:地域自治協議会やボランティア等、地域の協力による「共助」を行っている地域があることも聞くが、できる地域とできない地域が出てくるのではないか。今こそ「公助」でふれあい収集を実施する時期に来ている。その必要性に対する認識と課題について尋ねる。
市長:より身近な地域における支え合いが不可欠であるとの考えのもと、地域の協力による共助を基本に、その取り組みのひとつとして、地域の高齢者の社会参加の意欲を高める活動に注目し、介護予防の促進を図ることを目的とした、地域における支え合い事業の展開に向けた仕組みづくりを進めている。そのなかで、高齢者や障がい者などのごみ出しを含む日常生活上のお困りごとに対応していきたいと考えている。
阪本意見:市長は共助だけですすめようとしているが、これでは市民の困難さがわかっていない。今さら「共助」か「公助」かという議論をしている場合ではない。「共助」が無理な現実をしっかり見て、市長の決断を要望する。
6 こどもの自殺者の増加と包括的性教育について
厚生労働省が発表した去年1年間に自殺した人は暫定値で2万268人で、いまだ2万人を上回っています。一方で、小学生・中学生・高校生の自殺者は527人にのぼり、これまでで最も多かった令和4年の514人を上回って過去最多となりました。
奈良市において、子どもの命を守るための取り組みをどのように行っていくのか。また、いのちの大切さを学校教育のなかで学んでいくために、とても大切なこととして「性教育」があります。ユネスコは5歳からの「包括的性教育」を提唱していますが、日本の学習指導要領に基づく性教育では、「正しい性の知識を身につけることができるのか」、また、「性暴力を防ぐには不十分だ」という意見も聞いています。
阪本:奈良市における性教育の現状と、今後に向けた取り組みについて問う。
教育長:あらゆる教育活動において児童生徒一人ひとりが自尊感情を高め、「心の危機」を適切に発信できる力を育むとともに、自殺予防のための組織的な連携を密に進めていくことで、児童生徒や保護者が相談しやすい環境を整え、全ての児童生徒の命を守る取組を進めてまいりたい。
教育長:学校における児童生徒への性に関する指導にあたっては、自他の生命を大切にする心情を育むとともに、性に関する基礎的、基本的な内容を、児童生徒の実態や課題に応じながら、教育活動全般を通じて指導してきている。
教育長:今後も、大切な教育課題の一つとして、ジェンダー平等や性の多様性を含む人権尊重を基盤とした性教育に取り組んでまいりたい。
阪本意見:いのちは一番大切なもの、性教育は「いのちの学習」をすることであり、身体の仕組みを科学的にまなぶことからはじまります。ユネスコがいう「包括的性教育」は、身体の仕組みだけでなく性の多様性、ジェンダー平等など人権を基礎とした幅広いテーマを含む性教育のことで、今後取り組むべき方向を示すものだと思っています。ぜひ、奈良市においても、参考にしながら幅広く性教育に取組んでいただきたいと思います。
7 奈良市公共施設等総合管理計画について
8 外郭団体職員の処遇改善について
(2025.3.6)
定例議会
常任委員会


3月議会議案・予算説明会
2月20日の「内示会」で3月議会の議案が示されました。来年度の予算、今年度補正予算、条例改正等です。予算の議会がいよいよ始まります。
それに続けて2月21日は予算説明会でしたが、福祉部から調書に基づき各課交代で説明していただきました。
事業数がとても多くて驚きます。高齢者、障がい者、介護保険等、奈良市の福祉行政を支える職員の皆さんの姿が見えてくる気がしました。
(福祉部は女性の課長が多く、7つの課のうち5人が女性課長。ケアは女性に向いてる・・・?
ちょっと気になりました。)
(2025.2.21)
【2月5日 行財政改革及び公共施設等検討特別委員会】
請願第11号請願第11号(若草中学校区における学校規模適正化計画に関する請願)審査・阪本質疑
今回審査では、昨年11月6日に今回の請願が出されてから、請願提出者に対して何らかの対応をしてきたのか、鼓阪小学校PTAから反対の声がある中で、今後どのように対応を行なっていくのか、市の姿勢を質しました。
奈良市としての説明責任と、すすめるにあたってのプロセスの透明性が問われています。「何回説明した」かではなく、地元が納得いくまで説明を続ける必要があるのではないか。合意形成に向け、市は説明責任を果たすべきであると考えます。また、反対意見を無視したり、ねじ伏せたりせず、「対話を重ねてすすめていく」という答弁があり、それをしっかり確認したい。あらゆる機会を通じて対話を重ねて行くことを要望しました。
(2025.2.5)
【2月5日 行財政改革及び公共施設等検討特別委員会】
塩漬け土地と「三セク債」(第三セクター等改革推進債)について
阪本:土地開発公社解散に伴う「三セク債」の残高と土地売却の進捗状況は。
※事業目的も曖昧なまま、不要不急の土地を市土地開発公社が相場より高い値段で購入
し、簿価と実際の価格との間で、総額187億9千3百万円の含み損が生じるに至ったこ
とにより、市が「三セク債」(土地開発公社などの第三セクター・地方公社の損失補
償・債務保証等の整理のために行なった借り入れ)を発行して代理弁済し、それを20
年かけて返済(H24年から返済スタート)。
市(財政課長):R5年度決算では、残高が約78億円。土地は21事業でそれぞれ管理されており、現状は27万1千㎡の総面積の内、売却できたのは7500㎡、貸し付けしているのは1600㎡。
阪本:売却できたのが2.75%、貸し付け利用しているのが0.58%で、残り96%あまりが手つかずで残っているということだ。このことを市としてどこが把握しているのか。「事業」を担当している各課任せでいいのか。土地開発公社解散(2013年3月)から12年、土地取得から20年以上も事業化・売却できないままになっている土地を各課任せにしていていいのか。
市(鈴木副市長):土地の目的に応じて担当各課が管理し、総務部で総括している。
阪本:担当課任せの今の状況では、これ以上進まないのは自明のことだ。返済が終わればそれでおしまいということにならないよう、現状把握と事業化の可能性を真剣に探るべきであり、誰も責任をとらないということにならないよう、すすめることを強く要望する。
(2025.2.5)
定例議会
常任委員会

【1月27日 厚生消防委員会・阪本質疑】
(1)成年後見制度について(福祉政策課・長寿福祉課)
前回終活相談の窓口をわかりやすく設置してほしい、ということを質問しました。今回はもうひとつ終活に関連することとして「成年後見制度」について、高齢に焦点を絞って質問しました。
●法定後見と任意後見があるが、成年後見制度を年間どれくらいの方が利用されているのか。そして、身寄りのない人が増加していることが背景に、後見開始の審判を申し立てる人がいない場合に行われる「市長申立」も増加傾向にあることが明らかになりました。
●また、日常生活自立支援事業は「日常的な金銭管理」、成年後見制度は「すべての財産管理」という点で大きく違うし、成年後見は契約等の法律行為を援助する、その点が大きく違う。また、家庭裁判所の決定を待たなくてよい、という点では、支援者・利用者がアクセスしやすいのが「日常生活自立支援事業」だと受け止めました。
●そして、判断能力を失う前に、自らの意志に基づいて後見人を選んでおく「任意後見制度」は、これからの時代に、自己決定を尊重する仕組みとして大変意義あるものと考えます。
質問に対する市の答弁で任意後見は2%程度でした。もっと利用が広がればいいと考えるが、そのためには、どのような課題があると考えるか。市の姿勢を質しました。
●任意後見制度の利用増加のためには、まずは市民に広報することですが、「自己決定」という点はもっと大きく広報周知してほしいところです。そしてどこへ相談に行ったらいいのか、費用はかかるのか、そういう初歩的な情報からはじめて、高齢者に限らず幅広い年齢層に広く広報するよう求めました。
●さらに、今後、親族がいない高齢者が増加することから、親族に代わる人が成年後見制度の担い手になっていかなくてはなりません。十分な受け皿となるために市民後見人の養成・確保に今後も取り組んで行くよう求めました。
(2)放課後デイサービスについて(障がい福祉課)
放課後等デイサービスは、学齢期の障害を持つ子どもを対象に発達支援を提供するものとして保護者や関係機関に認知が広がったことから、いま事業所数、利用者数とも増加していると聞いています。
現状と、利用日数の増加を求め、質問しました。
●前年度(2023年度)と比べても利用者数が1~2割増加傾向にあること、平均利用日数が8日であることがわかりましたが、例えば東大阪市で小学生が23日利用できていたのに、奈良市へ来た時に最大9日しか利用できないことになっているという話をお聞きしました。奈良市が上限を9日としているその理由は何か。市の姿勢を質しました。
●また、答弁から約3分の1の利用者が上限日数を超えているということがわかりました。上限を超える手続きに必要な相談支援員さんが少ないという問題もあり、上限日数の見直しを行う必要があります。
●そして、市からの答弁で、「重度の障害のある児童も含めて個々の障害の状態や発達の状況、障害の特性等に応じた発達上のニーズに合わせ、本人への発達支援や、発達の基盤となる家族への支援を行う役割のほか、こどもや家庭に関わる関係機関と連携を図りながら、こどもや家族を包括的に支援する役割を果たすべきものであると考えております。」と、本人への発達支援と家族への支援の両方について、市の言及を引き出せました。
●さらに市からは「放課後等デイサービス利用の基本的な考え方を検討してまいりたい」という答弁がありました。家庭の環境が大きく変わり、2000年ごろを境に、共働き世帯が専業主婦家庭を上回っています。こういった社会的な背景の変化にどう対応していくのか、検討が必要ではないかと考えています。
利用日数についても、厚労省の全国調査では23日利用している人が42%いるとのことから、23日を上限にしている自治体も結構多いと容易に想像できます。日数を増やせば自治体負担も増えることになり、難しいところですが、少なくとも小学生についても、中学生と同じ18日に見直していくことはできるのではないか、と考えますので、ぜひ検討することを求めました。
(2025.1.17)



